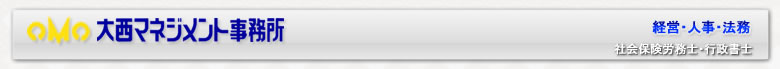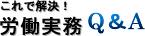
労災民事訴訟と過失相殺
|
Q. 労働災害が起きたとき、労災保険の給付の価額の限度を超える損害について、使用者は、労働者側から民法上の損害賠償責任を追及される可能性があります。その法的構成については、安全配慮義務(労契法5条)違反を理由とする債務不履行(民法415条)と不法行為(民法709条、715条)の2つ。労働者の業務と損害の発生の因果関係が肯定されても、本人の落度や基礎疾患等があった場合に、過失相殺され、損害額が調整されることがあるのでしょうか。 |
A. 労働災害について被災労働者側に過失がある場合、安全配慮義務違反による債務不履行であれば、「裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める」(民法418条)と規定。不法行為であれば、「裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」(民法722条2項)とされています。判例は、一般論として労働者側の要因を一定程度斟酌して過失相殺を認めつつ、使用者側の日常の業務管理上の配慮や労働者の健康把握義務を重視して、これを否定するケースもあります。 |
|
◆安全配慮義務の明確化 判例は、雇用契約上の安全配慮義務について、「労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」と定義していました(川義事件最 最判昭59・4・10)。 ◆因果関係と義務違反 労働災害について損害賠償請求を行う民事訴訟では、まず、労働者の業務と当該負傷、疾病または死亡との間の「相当因果関係」が認められなければなりません。労災保険給付でいうところの「業務起因性」があることが第1の要件です。また、使用者において、安全配慮義務違反(債務不履行)または過失による注意義務違反(不法行為)の認定が第2の要件となります。 ◆過失相殺の可否 安全配慮義務違反と不法行為の過失相殺の規定について、法文上の違いに合理的根拠はないというのが定説です。そこで、労災民事訴訟において、業務と損害の発生との因果関係が肯定されても、さらに本人の性格や病状不申告等の要因を一定程度斟酌して、過失相殺ないし同法理の類推適用により損害額の調整ができないかが問題となります。 |