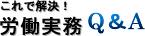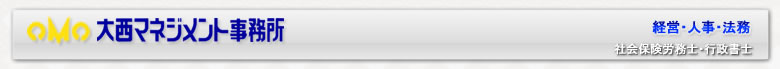◆失業給付(基本手当)のルール
雇用保険の基本手当の受給資格が認められるためには、つぎの要件を満たすことが必要。
第1は、被保険者が失業していること。失業とは、「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」(雇用保険法4条3項)をいいます。
第2に、離職日以前2年間に、被保険者であった月(賃金支払の基礎となった日が11日以上ある月)が通算して12ヵ月以上あること(同法13条、14条)。
ただし、特定受給資格者(倒産、事業縮小、解雇)等については、離職日以前1年間に通算して6ヵ月以上、に緩和されます。
基本手当はいくらぐらいか。離職日以前の6ヵ月間の賃金(賞与は除く)の総額を180で割った額を「賃金日額」とし、この賃金日額の45%~ 80%の額が、基本手当の日額となります。
◆雇用保険の主な改正点
(1)教育訓練給付金の給付率見直し
働く人の能力向上を目的とする「教育訓練給付金]。24年10月から、厚生労働省で指定した講座で学び、条件を満たせば受け取れる教育訓練給付金の給付率が引き上げられました。
再就職や早期のキャリア形成のための「特定一般教育訓練」(40%→50%)、中長期的なキャリア形成を後押しする「専門実践教育訓練」(70%→80%) が、それぞれ10%上乗せされました。
(2)自己都合退職での給付制限期間の短縮
自己都合で退職した人には、失業給付(基本手当)を受けられない給付制限期間があります。ハローワークで求職を申し込んだ後、7日間の「待期期間」を経過する必要があり、自己都合で退職した人は、これに加えて原則2ヵ月は給付が受けられませんでした。
今年の4月以降は、この給付制限期間が原則1ヵ月に短縮。さらに失業期間中や退職から遡って1年以内に教育訓練を受けた場合にはこの制限が解除されます。転職のハードルがかなり下げられることに。
(3)「教育訓練休暇給付金」の創設
今年の10月から、「教育訓練休暇給付金」が創設されます。在職しながら教育訓練を受けるため、無給の休暇を取る人に給付される制度。辞めた場合に受けられる失業給付と同額です。働く人の生活費への心配を減らし、スキルアップに集中できるようにするためです。現在、1万6000の講座があります。
(4)雇用保険の適用拡大
少し先になりますが、法改正の目玉として注目を集めているのが28年10月からの適用拡大。雇用保険加入には労働時間が週に20時間以上という条件があります。それが週10時間以上に広げられるのです。総務省の労働力調査によると、23年時点で週に10~19時間働く人は約506万人いるといわれています。失業給付や教育訓練など、働き手の安心につながる仕組みが充実します。
|