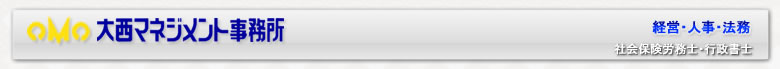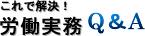
拘禁刑
|
Q. 労働基準法は、その大部分の条項について、違反行為に罰則があります。罰則の内容については、第117条から121条までの条文に一括して規定。その中で最も重い罰則が、法5条の規定に違反する「強制労働の禁止」です。「第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する」(117条)と定めていました。懲役と禁錮が廃止され、拘禁刑に一元化されると聞いています。この場合の懲役も拘禁刑になりますね。 |
A. 従来の懲役と禁錮は、刑務作業の義務があるか否かの違い。懲役の受刑者には刑務作業が義務づけられ、禁錮の受刑者は任意でした。懲役と禁錮が拘禁刑に一元化される背景には、実態として懲役と禁錮の差がなくなっていた実情があります。禁錮の受刑者は少なく、大部分が刑務作業を任意で行っていました。拘禁刑への一元化は、2022年6月17日公布の「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)によるもの。施行日は、今年(2025年)の6月1日。労働基準法の罰則も同様です。 |
|
◆懲役と禁錮の異同 自由を剥奪する刑罰として、かつて刑法典は、懲役と禁錮の2種類を定めていました。懲役と禁錮は、いずれも刑事施設に拘置する点では共通していますが、懲役の場合は「所定の作業を行わせる」として刑務作業を課す、という相違点がありました。 ◆拘禁刑への一元化 拘禁刑は、受刑者を刑事施設に拘置してその自由を剥奪したうえで、その改善更生・社会復帰を図るために必要な作業を行わせ、また、必要な指導を行うものです(改正刑法12条2項、3項)。これは、作業及び指導を常に義務づけるのではなく、個々の受刑者の特性に応じて、その改善更生を図るために必要なかたちで、作業と指導とを効果的に組み合わせた処遇を行うことを可能とするものです。拘禁刑では、刑務作業の要否は、受刑者ごとに決定されます。
|