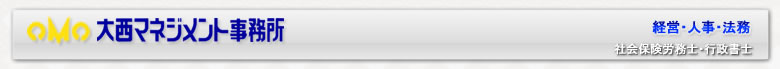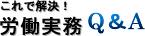
退職金の減額・不支給条項
|
Q. 懲戒解雇は、制裁としての懲戒処分の極刑であり、使用者の一方的意思表示により労働者を企業外に放逐する処分。多くの企業では、就業規則等において、「懲戒解雇された者に対しては、退職金を不支給または減額する」という条項を置いています。老後に必要となる生活資金として2000万円は必要ということが話題になりましたが、退職金がゼロになると老後のライフプランに与える影響は小さくありません。この場合の法的論点や判例はどうなっていますか。 |
A. 退職金に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項であり(労基法89条3号の2)、就業規則等で支払条件が明確に定められていれば、「労働の対償」としての賃金に該当し(同法11条)、退職金請求権は法的保護を受けます。退職金には、賃金後払い的性格や功労報償的性格があるとされ、懲戒解雇の場合の退職金の減額・不支給条項の合理性や適法性と適用の当否が争われるケースがよくあります。学説と判例を概観してみましょう。 |
|
◆退職金の減額・不支給条項の適法性 退職金の減額・不支給条項の適法性は、退職金の法的性格や退職金の発生時期をどう捉えるかによって、見解が分かれます。 ◆小田急電鉄事件(東京高判平15・12・11) 鉄道会社の従業員が、休日に他社の鉄道の車内において、痴漢行為(迷惑防止条例違反)を行い逮捕、起訴され、有罪判決を受けた。会社は従業員を懲戒解雇し、就業規則の規定により退職金を不支給とする。一審は懲戒解雇および退職金の不支給を有効と判断したため、本人が高裁へ控訴した事案。 ◆宮城県・県教委事件(最判令5・6・27) 30年間誠実に働いてきた公立高校の教員が、酒気帯び運転で物損事故を起こし、逮捕され罰金刑に。県教委は、懲戒免職処分とし、退職手当に関する条例にもとづき退職金は全額不支給。二審の高裁は、「大幅な減額はやむを得ない」としつつ、教員の勤務状況や反省の深さを重視して、退職金の3割相当を支給すべしとした。双方がこれを不服として最高裁へ上告した事案。 |